大和国聖林寺の十一面観音立像について調べていた際、大神神社の近くの平等寺に聖林寺十一面観音立像と瓜二つの像が安置されていることを知りました。
Googleマップやネット上の記事を調べると、車で向かうのが難儀であるような印象を持ってしまいました。
しかも、この十一面観音立像を拝観するには「予約が必要」ということもあり、月日が恵果してしまいました。
今回の大和国遠征において、初めて大和国聖林寺を参詣しました。
そこから大神神社に向かったのですが、大神神社境内を徘徊していたところ
「三輪山 平等寺」
の表示と遭遇しました。

古く、かなり損傷が激しい築地塀の残痕の傍らに立てられていました。
この位置から、それ程遠くはなさそうです。


それにしても、かなり年季が入っている築地塀です。
調べて何か判明したら、また話題にしますね。
大神神社から平等寺に向かっている途中、右手側の視界が開けてきました。

左手側に見えるのが畝傍山、右手側に見えるのが耳成山です。
残念ながら香具山は民家と藪の存在で見えません。
もうちょい進むと

伊勢街道の先に、キレイな形の耳成山が見えています。
ここから歩いて間もなくでしたよ。
大和国平等寺の入口です。

この参道を進むと

山門前に到着します。
山門には「三輪山」の額が掲げられています。

この山門を潜ったら、寺の由緒書がありました。
以下の内容でした。
「
三輪山平等寺由緒
三輪山平等寺は、その開基を聖徳太子と伝え、永遠の平和を祈願する霊場として
創建されました。鎌倉時代の初頭、中興の祖、慶円上人(三輪上人1140~12
23)を迎えるに及び、東西500m、南北330mの境内に、本堂、護摩堂、御
影堂、一切経堂、開山堂、赤門、鐘楼堂のほか、十二坊舎の大伽藍有し三輪社奥
の院として、由緒ある銘札でありました。
平等寺は三輪別所とも呼ばれ、高徳の上人を中心に、仏法の奥義をきわめんとす
る行学一如の根本道場として栄えました。東大寺の宗性は嘉禎元年(1235年)
八月二十日に平等寺において法華、唯識、般若三観抄を写し、幾度も当山を訪れた
ことや、建長二年(1250年)正月、西大寺の叡尊も三輪別所一乗上人の禅室に
参詣した史実も明らかで、鎌倉時代の平等寺には、仏法、学問の奥義を求めて多く
の人びとが参詣しました、
室町、江戸時代には醍醐寺三宝院、南都興福寺とも深く関係し、八十石の朱印地
を持ち修験道の霊地でもありました。また、計帳五年(1600年)九月十五日関
ヶ原の合戦で敗れた薩摩の領主、島津義弘主従がこの寺に逃げ込み十一月二十八日
まで七十日間滞在し無事帰国されました。しかし残念なことに、明治政府になって、
政府の廃仏毀釈(仏を廃し神を敬する)の令きびしく、大神神社の神宮寺であった
平等寺は、ことさらにそのあらしを強く受け、有名な金屋の石仏をはじめ、六十一体
にのぼる 仏像が他所に運び出され、堂塔ことごとく整理を迫られましたが、幸いに
その直後小西氏より現境内地の寄進を受け最高の道が開かれ、覚信和尚や町内有志
の方々の努力により塔頭の一部を境内に移し、本尊秘仏十一面観世音菩薩、三輪不
動尊、慶円上人像、仏足石等が守られ、梁天和尚が翠松庵の寺号を移し禅曹洞宗に
改宗し法燈を護持しました。聖徳太子をはじめ歴住諸大和尚の自思に報いるべく平等
寺の再興のために微力ながら勧進托鉢行を続けてきましたが、廃仏毀釈より100
年目を迎えた昭和五十二年六月四日付て平等寺と寺号が復興され、幾十万の人々よ
りご喜捨を賜わり、ありがたくも本堂、鐘楼堂、 鎮守堂、翠松閣、釈迦堂(二重塔)
の復興をはじめ前立本尊十一面観世音菩薩のご造立をみることができましたのは、
すべて神仏のご加護と皆々様の真心からなる奉賛のたまものと深く感謝いたして
おります。
ご参詣の皆様、ご奉賛の皆様方にはお釈迦さまの自思の光明が無限に照り輝きます
ように、心からお祈り申しあげます。
慶円禅観上人800回大遠忌記念
平成二十六年(2014年)四月八日
三輪山平等寺 七十四代 丸子孝法 合掌
」
山門を潜って右手側には

鐘楼が建っています。
1987(昭和62)年の再建だそうです。
手水所には

龍(ドラゴン)が居ましたよ。
居心地の良さを感じました。
目線を上げると・・・

聖徳太子(厩戸皇子)の銅像が立っていました。
大和国法隆寺に足繁く通う様になってから、事前に調べていなくても聖徳太子関連史蹟に辿り着いちゃいます(笑)。
聖徳太子関連の真否は定かではありませんがね。
あの有名な、いわゆる「聖徳太子像」を立体化した像の様です。

1987(昭和62)年に再建された本堂です。
この本堂には
本尊前立十一面観世音菩薩像
として、平等寺の御住職様の発願により1987(昭和62)年の本堂再建に合わせ、聖林寺十一面観音のデータを基に樹齢1500年の檜の一木造で製作されたものだそうです。
本堂内陣に参詣するためには事前に予約が必要だそうです。
今回の平等寺参詣はm偶々流れに乗っかったものでしたから、当然予約はしておりませ
予約は次の機会にねっ。
本堂前の石柱は

「令和四年」(2022)の年紀が刻まれていました。
忘れていなければ次回の参詣時に文字を見ておきますね。
境内の各所に
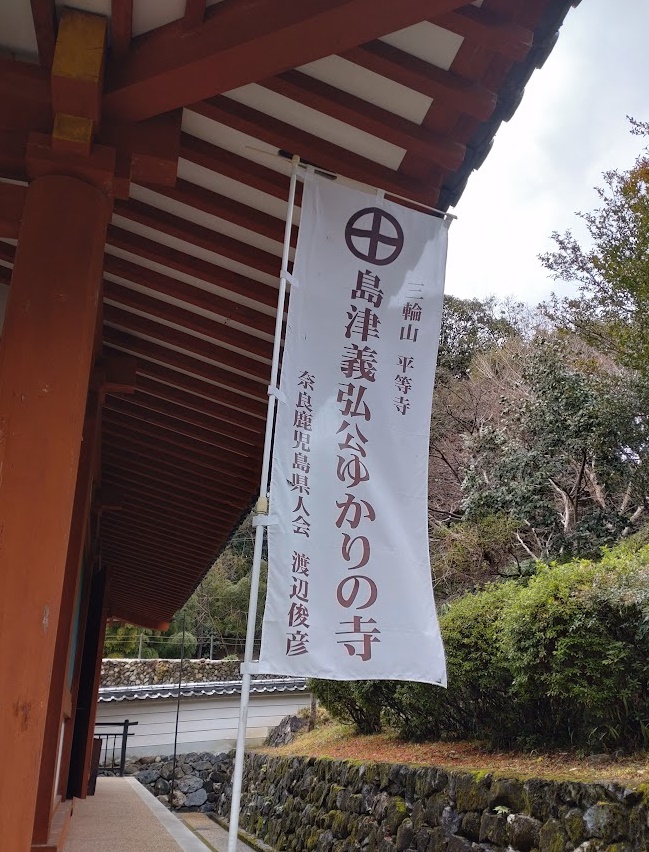
「島津義弘ゆかりの寺」の文字が入った幟が立てられていました。
関ヶ原の敗戦後、島津隊は大和国の山中を経由して摂津国大坂から乗船して薩摩間へと逃げ帰ったそうです。
ここに隠れていたかっ!
これは参詣したことによって偶然知った情報でした。
本堂前を通過すると、不動堂が見えてきます。

堂内に入ることはできませんが、空海作と伝わる三輪不動尊や、役小角像・「理源大師」聖宝像が納められているといいます。

「降魔殿」の額が掲げられています。
魔物を降伏(ごうぶく)するという意でしょうな。
斜め後方には

2004(平成16)年に再建された二重塔が配されています。
釈迦堂とも呼ばれています。
古の木組が差異迂言されています。

朱塗りの柱、白壁、緑色の連子窓と、大和国の建造物の特徴が嬉しいですね。
二重塔(釈迦堂)の前には

仏足石が設置されています。
実際には金網で覆われているのですが、網目の隙間にレンズを合わせて撮りました。
次は、全体が写るように撮りますね。
平等寺二重塔は小規模な塔で、

その回りを巡ることができます。
なので、グルッと回ってみるのです。

雨は止んで曇天状態でしたが、随所に青空が見え始めていました。

青空の下、平等寺二重塔の映えた姿を見たいので、また参詣します。
チラチラと写っていますが、二重塔の回りには十六羅漢が座っているのですよ。



それぞれが個性ある姿で座していますyね。
こうして釈迦仏を抱いているのは、人間にも仏性が備わっているということを表現しているのでしょうが、

これは気持ちワルイ・・・。

「羅怙羅尊者」(らごらそんじゃ)という、釈迦の子で十大弟子且つ十六羅漢に数えられています。
釈迦仏を抱いている羅漢と同義の姿なのでしょうがねぇ・・・。
仏教の教えは難しいものです。
境内図に「善如龍王の池」という表記があり、聖徳太子/空海だけぢゃなく善如龍王にも招かれている事を実感したのですが、

このコンクリート造の太鼓橋が架かっているのは「心字蓮池」という説明でした。
どうなって居いのでしょうかね、解りません。
無茶しても解りませんよ。
必要があれば、聖徳太子か空海か善如龍王の何方かがヒントをくれることでしょう。
太鼓橋の左手側に、

最早これは〝怪奇現象〟でしょう(笑)。
雨天や降雪時、遅くて暗くなった際、こりゃぁおっかないですよ。
善如龍王が居るのであれば

逢いたかったのにぃ・・・。
またねっ、大和国平等寺に訪れたいと思いました。
島津義弘が逃げ込んだという点を除けば、とても良い雰囲気でしたからね。

次回、もしくは今後の参詣時では、拝観予約を入れて聖林寺十一面観音の兄弟と対面したいと考えていますぞ。
当サイト内のすべてのコンテンツについて、その全部または一部を許可なく複製・転載・商業利用することを禁じます。
All contents copyright (C)2020-2025 KAWAGOE Imperial Palace Entertainment Institute / allrights reserved